【実施報告】 ELSI HIROSHIMA ワークショップ 2025
広島大学共創科学基盤センター(ELSI Hiroshima)は、大阪大学社会技術共創研究センター(ELSI センター)および広島大学ゲノム編集先端人材育成プログラムとともに、2025年3月17日(月)から18日(火)にかけて「ELSI HIROSHIMA ワークショップ 2025」を開催しました(於:広島大学東千田キャンパス・地域連携フロア SENDA LAB)。本ワークショップは昨年度に続き2回目の開催となり、複数の大学や組織から講師・受講生・オブザーバー等を含む総勢62名(うち受講生は17名)が参加し、昨年度の約2倍の規模で大きな盛り上がりを見せました。2日間にわたるプログラムでは、計4つの講演・パネルディスカッションが行われ、ELSI/RRI(Ethical, Legal, and Social Issues/Responsible Research and Innovation)人材の育成およびネットワーク形成の促進を目的として、多様な視点や最新の取り組みが共有されました。
3月17日(月)11:00-18:00(1日目)
初日は、まず「ELSI/RRIとは?」をテーマとした講演が行われ、国立研究開発法人科学技術振興機構フェローの濱田志穂氏が登壇されました。講演では、ELSI/RRIの概念整理や海外における事例紹介、第7期科学技術・イノベーション基本計画の議論状況などが概説され、総合知の重要性や日本のELSI/RRIが抱える課題・強みに関して活発な意見交換が行われました。
続く「全国ELSIセンターの取り組み」と題したセッションでは、各大学ELSIセンターの紹介の後、大阪大学COデザインセンターの八木絵香氏の司会のもとパネルディスカッションが実施されました。大阪大学社会技術共創研究センターの岸本充生氏、神戸大学生命・自然科学ELSI研究プロジェクト(KOBELSI)の茶谷直人氏、広島大学共創科学基盤センターの澤井努氏、中央大学ELSIセンターの飯塚三保子氏(オンライン参加)、新潟大学ELSIセンターの久間木寧子氏から、それぞれのセンターが掲げるビジョンや研究活動の特徴をご紹介いただきました。特に、産学連携や学際的研究を推進する取り組み、若手研究者育成への支援体制など、各大学ならではのアプローチが示されました。パネルディスカッションでは、研究者がELSI/RRI研究に着手する利点や必要な準備、さらにはELSIセンターという拠点を設ける意義などについて具体的に議論されました。
3月18日(火)9:30-16:10(2日目)
2日目最初のセッション「市民/患者と共につくる社会を考える」では、3名の講師により、実践例を交え、多様な科学技術分野での市民参画や患者参加型の研究についてご講演いただきました。多摩大学の樋笠尭士氏は、自動運転技術に関するこども向けワークショップなどを紹介し、科学技術が社会に受け入れられるための「社会的受容性」を高める手段として、双方向のコミュニケーションが重要であると強調。大阪大学大学院医学系研究科の古結敦士氏は、患者が研究参画者として議論や論文執筆にまで関与する事例をもとに、PPI(Patient and Public Involvement)の意義や課題に言及されました。東京大学医学系研究科の中澤栄輔氏は、脳科学や若年性アルツハイマー病など多様なテーマでのELSI研究を通じ、患者・市民の意見を取り入れる一方で「共謀的関係」によるリスク認知の歪みが生じる可能性を指摘されました。パネルディスカッションでは、市民や患者の代表性をどう確保するか、専門家が議論を主導することの是非など、科学技術コミュニケーション全般にかかわる論点が熱心に交わされました。
最後のセッション「ELSI/RRI分野におけるキャリアパス」では、東京通信大学の福士珠美氏、大阪大学社会技術共創研究センターの水町衣里氏、株式会社メルカリR4Dの藤本翔一氏が、自らのキャリアの歩みを振り返りながら、異なる組織や分野を横断して活躍するヒントを語ってくださいました。人との縁を大切にし、好奇心を原動力として行動すること、環境や人々のニーズを敏感に捉えて柔軟に変化することなど、具体的なエピソードを交えて示されたアドバイスには、参加者からも大きな共感と関心が寄せられました。また企業での研究活動においては、意思決定を握る関係者の早期巻き込みや、双方のメリットの明確化の重要性が指摘されていました。
今後に向けて
本ワークショップには人文系を中心とする多様な専門分野の受講生が参加し、自分の研究とELSI/RRI研究との連関を模索する姿が多く見られました。一方で講師陣は、急速に発展する科学技術と社会を結びつけるELSI/RRI研究の意義を再確認するとともに、研究者コミュニティ全体への理解と協力とを広げていく必要性を強調していました。本ワークショップでは、参加者同士が分野を越えて交流し、新たな連携の種を見出す貴重な機会となりました。今後もこのような学際的な交流の場を提供し、ELSI/RRI人材の育成およびネットワーク構築に貢献する取り組みを共創科学基盤センターでは続けていきます。
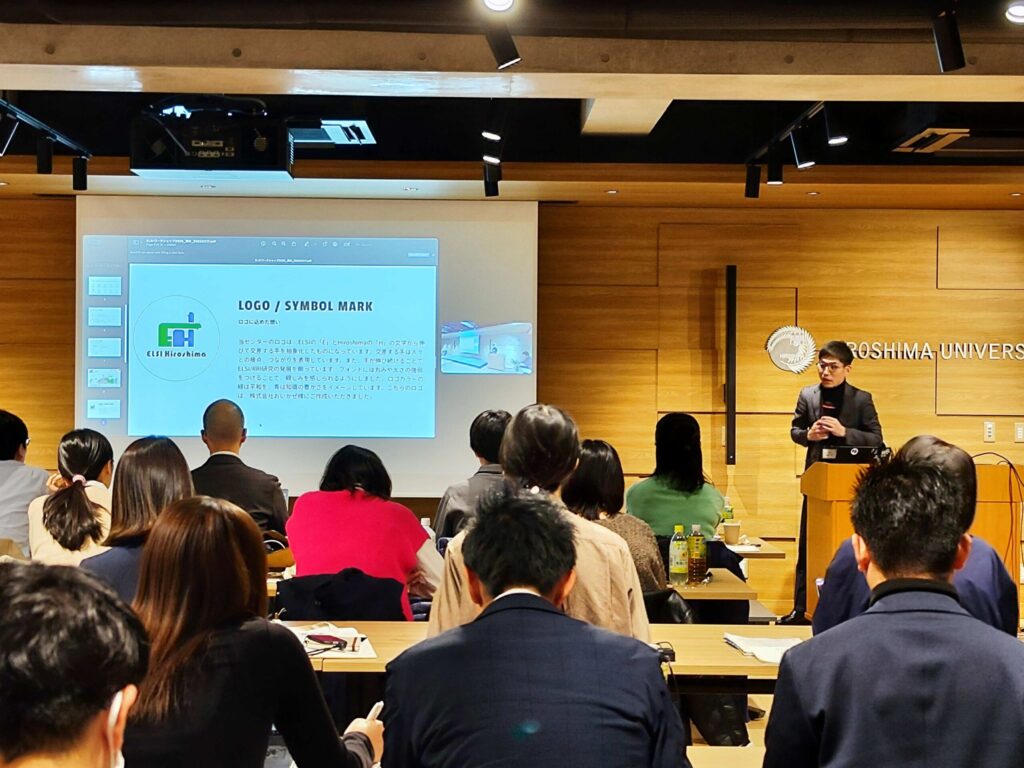

*プログラムはこちら

